大滝山 三重ノ塔(勢見山、大滝山)

眉山は昔から徳島のシンボルとして親しまれております。
今回は阿波古代史ネタ、神社巡りから離れて、明治末期から大正初期にかけての眉山を追ってみたいと思います。
その昔、眉山の山腹に三重塔があったのはご存知でしょうか。


【三重ノ塔】


【不動滝上の石段】
当時は大滝山の麓から山腹にかけてが一番の賑わいがあったようで、春日神社横の薬師堂には焼き餅屋。


【現在の春日神社】
そして石段を登ると不動滝と不動尊。

【不動滝の不動尊】
さらに上には白糸滝と呼ばれた滝があり、風流な料亭が数軒店を構えておりました。そこには富田町、敬台寺近辺の芸妓達が頻繁に呼ばれていたようです。

かつては大滝山でも東側にあたる「天神社」の上付近を桃山、東山と呼んだりしていたそうです。


【現在の天神社】
瑞巌寺、国瑞彦神社の周辺もそれにあたります。
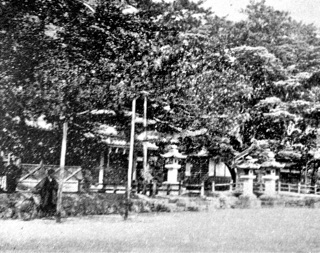
【昔の富田八幡神社と国瑞彦神社】




【現在の国瑞彦神社】


【現在の忌部神社】

【現在の金比羅宮】

さて、勢見山から大滝山に続く道があるのをご存知でしょうか?
当時の資料では…
「佐古より起點し眉山の中腹を貫通し勢見山に至る間に坦々らる道路を開墾し其兩側に櫻樹楓樹 梅樹等敷萬本を配置し其他四季折々の樹木及草花を栽 植するにあり」と説明していることから、主な開発内容が新道開発と沿道への植樹であることがわかる。
前置きが長くなって肝心の三重ノ塔の話をしようとしていたのを忘れていました… テーマの三重ノ塔の話に戻ります。
三重ノ塔は「持明院 三重ノ塔」
蜂須賀入国の際に阿波の各地域や旧領地より寺院を移転させたことによります。「持明院」は「大滝山 建治寺」と号す。
持明院はもともと勝瑞にあったようで後々、薬師像二駆と共に入田町の西龍王山に建治寺に移遷。それを大滝山の現地に移動させたものです。

【入田町 建治寺の岩窟(薬師像 安置場所)】
この時に春日神社も一緒に入田町から移動させたんです。

【入田町 春日神社跡】
江戸期の持明院は藩の寺院の保護も厚く、寺院経営も安定してあおましたが、幕末期になると世俗化するとともに伽藍を維持する経費が膨らみ困窮を極めたそうです。
そしてとうとう昭和20年の徳島大空襲で三重ノ塔は破壊され、一切を消失したまま現在に至るのです。
大戦前までは眉山のシンボルとされた三重ノ塔。



眉山の麓に訪れる機会がある時は是非、大滝山界隈へ。
滝の焼き餅を食べて昔の繁栄の名残りを感じながら散策するのもいいですよ。
大滝山関連では神武天皇像の過去記事もあります。よかったらどうぞ。



